�@a. �����푈
�b�ߔ_���푈�Ɠ��������̏o��
�� �ɓ����t�̐����Ƌ�Y
 �@1892�N8���A��ɓ��������t����������ƁA���ď����Ƃ̕s�����������Ɏ��|����A1893�N7��5���������@���O���i���}�j�͏��������j���t�c�ɒ�o���A19���Ɉɓ��Ɨ������V�c�ɉ���āA���������j�̍ى��܂����B���̓C�M���X�A�h�C�c�A�A�����J��D�悷��Ƃ��܂������A�h�C�c�A�A�����J�͏��ɓI�ł��������߁A�C�M���X�Ƃ̂��ɓ��邱�ƂƂȂ�܂����B
�@1892�N8���A��ɓ��������t����������ƁA���ď����Ƃ̕s�����������Ɏ��|����A1893�N7��5���������@���O���i���}�j�͏��������j���t�c�ɒ�o���A19���Ɉɓ��Ɨ������V�c�ɉ���āA���������j�̍ى��܂����B���̓C�M���X�A�h�C�c�A�A�����J��D�悷��Ƃ��܂������A�h�C�c�A�A�����J�͏��ɓI�ł��������߁A�C�M���X�Ƃ̂��ɓ��邱�ƂƂȂ�܂����B�@�������A��͓�ǂ̌������܂ފC�R�\�Z�ƐϋɓI�ȎY�ƐU����ЊQ�~���̐������������ϋɌ^�\�Z���c��ɒ�o�������{�ƁA����ߌ��E���͋x�{�i�R������܂ލs����p��ߖĒn�d�y�����s���Ƃ������}���̎咣�j�Ƃ������}�ƑΗ����܂����B�܂��A�����������߂����đΊO�d�h�����s����s���c�Ă��O�c�@�ɒ�o�������߁A1893�N12��30���O�c�@�͉��U����܂����B
�@�ΊO�d�h���͂͋c�Ȃ����炵�A���{�ɑË��I�Ȏ��R�}�͖��i�������̂́A�M���@���߉q�Ė����݂�𒆐S�Ƃ����ɓ����t�ᔻ���͂��`������A�S���̐V���G���L�҂��A�����đΊO�d�h�̎咣���x�����A�����{�C�^����������ߎ��ԑŊJ�̕��r��������@�Ɋׂ����ɓ����t�́A���p�Ԃ̏����������Ì����邱�Ƃ�������ŁA�ɓ��͓V�c�Ɖ�k����1894�N6��2�����O�c�@�����U���܂����B
�@�� �u���s����s�_�v�́A�W���[�i���X�g���x�h��̎G���w�����V�F�x���������̂ŁA�����I�^���ɂ���Č��s�̏��������Ɏ��s���邱�ƂŁA�ݓ��O���l�ɕs�ւ�^���A���S�ȏ������i���O�@���P�p�ƊŎ��匠�j�ւ̎����Ƃ��悤�Ƃ���咣�̂��ƁB
�� ���N�̓��w�ƃL���X�g��
 �@���w�ɑ���u���w�v�̐����ȗ�����p���ŁA�u�V�����v�����N�̐V�@�������܂�܂����B
�@���w�ɑ���u���w�v�̐����ȗ�����p���ŁA�u�V�����v�����N�̐V�@�������܂�܂����B���Q�Ɓ�
�E���{�Ɠ��A�W�A� �i�؍��L���X�g���ҁj
�E���w�E�V�����Ɠ��ꌴ��
�@1824�N�A�c�B�ɐ��܂ꂽ���ϋ���1860�N�Ɂu���w�v�������܂����B���w�͎���Ƃ��Ȃ���������̓_�ŃL���X�g���̉e�����܂������A�C�G�X�E�L���X�g�ɑ������鑶�݂͂Ȃ��A�l�X�̋~����ڎw���Ă���Ƃ͂����A�L���X�g���ɂ�����u���߁v�ɑ�������ϔO�����݂��܂����B
�@���w�͊����̏@���Ƃ͑S�����e��Ȃ����݂ł��������߁A���N���ǂ̓L���X�g���Ɠ��ꎋ���Ēe�����A1864�N3��10���ɛ��ϋ��͑�緂Ŏa��A���w�̌o�T�͏ċp����܂����B
�@���㋳�c���������́A���w�̌o�T���Ï��Ă����̂ŕ������\�ƂȂ�A�u�V��̎�͂킪�S��̈��v�ł���Ƃ��āu�l�́A���Ȃ킿�V�Ȃ��v�Ɛ����A1894�N�ɔނ�𒆐S�Ƃ����W�c���A���ė̒��N�N���ɑ��Đ�������R�^���ł������w�_���^���i���}�j���N����܂����B
�� �b�ߔ_���푈�i���w�̖I�N�j
�@���N�ł͊J����A1880�N��ɓ����̖f�Ջ����ɂ���āA�O���Y�ȕz�̗A���A���n����č��E�哤�̗A�o���}�����Ė��O�̕n�������i�݂܂����B����ɑ��Ē��N�����͍�����@�Ɋׂ��ĕn�����������O�ւ̑��łĂ��A�e�n�Ŗ������������܂����B
 �@���̍��A���N�Ŗ��O�ɉe���͂��������u���w�v�͑��㋳��������̂��ƂŁA���N�암��тɍL����A�������͐��{�̒e��������邽�߁u��S���C�v�̓��Ȏ�`�𓌊w���k�̋��߂܂����B�������A����Ŗ��O�̕ϊv�u���Ɋ��҂��铌�w�ْ[�h�����݂��A1894�N2���ɑS�����̍��q�n�тɂ���Õ��ŁA���w�ْ[�h�̎w�����S�{�����i���}�j���n���������՝��n���ɖI�N���܂����B
�@���̍��A���N�Ŗ��O�ɉe���͂��������u���w�v�͑��㋳��������̂��ƂŁA���N�암��тɍL����A�������͐��{�̒e��������邽�߁u��S���C�v�̓��Ȏ�`�𓌊w���k�̋��߂܂����B�������A����Ŗ��O�̕ϊv�u���Ɋ��҂��铌�w�ْ[�h�����݂��A1894�N2���ɑS�����̍��q�n�тɂ���Õ��ŁA���w�ْ[�h�̎w�����S�{�����i���}�j���n���������՝��n���ɖI�N���܂����B�@���̖I�N�͈ꎞ���܂�A4�����ɍĖI�N����ƁA�S�����A�������̓��w�ْ[�h�̎Q���ɂ��g�債�A���� 6�A7000�l�ƂȂ����ނ�͊���ɐi�����āA���͂��{��������œ|���A�����Ɏ���̒���ƕ������v�̎�����i���悤�Ƃ��܂����B
�@���w�_���R�̕���͉Γ�e�E�����Ƃ�����������ŁA�퓬�ɂ�����Ă��܂���ł������A���{�������̂��߂ɔh���������R��5��11���ɌÕ��߂��̉��y�q�����Ŕj��A�Â��ē��w�_�������̒����������𖽂���ꂽ���i�����z�F�S�����ƌc�����j�����g�^�[�M�z���̐V�������̋��R��5��27���Ɍ��ނ��A�S�B�̎��R�͐�ӂ��Ȃ��_���R��5��31���������������܂����B
�@�^�[�M�͔_���R��nj����āA6��1���ɐ��{�R�𗦂��đS�B��O�ɓ�������ƁA����ɖC���������A�_���R�͑����̋]���҂��o���Č��ނ���܂����B
�@���̌�A�x������J�n����A�_���R��27�����̕������v����������ɏ�B���邱�Ƃ������ɁA6��11�����a���ɉ����A�S�B����P�ނ��܂����B
�@���̑S�B�a���������̂́A�_�Ɋ����߂Â��_���R�̐�ӂ��ቺ�������ƂƁA�������R�̒��N�h����m��A�_���R�����{�R���푈�̊�@���@�m�����̂����R�ł����B
�@���{�̊O���ȂƗ��C�R�́A���w�}�̓�����S�����ł̖I�N�ɂ��ď������W���Ă��܂����B���w�_���R�����{�R��j�����Ƃ̏�`���ƁA�R�͂N�� �h�����A���N�ݗ����{�l�̕ی���������܂����B�܂��A���ω����Đ����h������A���{���h������K�v��������\�����邽�߁A���̏o���ɑ���R�o ���̉\�����������n�߂��̂ł��B
�@���N���{�͍������@�Ƒ�������A������������邽�߁A���ɔh�����˗����邱�Ƃ��c�_���āA���{�̑R�o�������O���Č��_���o�����ɂ��܂������A5��31���̔_���R�S�B��̂̕A���ւ̎ؕ��˗������ӂ����܂����B
�@���{���͐��R�o���̏����͐��M���瓾�܂����B6��1���ɓ��{���g�ُ��L���A�i�M���A3���ɂ������\�㗝���g���A���ꂼ���͐��M��K�ˁA���ǂ��c�_���A�����̏o���ɂ��Ęb�������܂����B
�@�͐��M�͓A�Ɖ�k������A���{���ɂ͍���̒��N�����𗘗p���Đϋɍ���̂�ӌ��͂Ȃ��A���g�فE�������̕ی��ړI�Ƃ�����{���̏o���K�͕͂����ꒆ�����Ȃ��Ǝv����A����ē����Փ˂̉\���͔����Ɣ��f���A�����͂ɏo���˗��̓d���ł��܂����B
�@�����͓A���͐��M���瓾�������A�u�S�B����������R�̎�ɗ������B���N���{�͐��̉��R�����߂����͐��M��������v�Ƃ����d���O���Ȃɔ��M����A����ɂ����6��2���̊t�c�ňɓ�����x�ڂ̒鍑�c��̉��U�����߁A���N�ւ̏o�������܂����̂ł��B
�� �����푈�J��O
�@�@ �ɓ��̋����_�Ɨ����O���̋��d�_
�@�o���ɓ��ݐ����ɓ��́A�����������ێ������ƌ����s���Ē��N�̓������v�ɒ��肵�A���N�𐴂Ɠ��{�̋��ʂ̐��͌��ɂ��悤�Ƃ��A���R�Ƃ̏Փ� �����j���Ƃ�܂����B����ɑ��āA�����O���͓��{�����ɑR���ďo�����u���N�ɑ��錠�͂̕��ς��ێ��v����K�v������Əq�ׂāA�u�t���F���̋c�Ɏ^ ���v���ďo�������܂�܂����B�t���̂�������A�o���̐^�̖ړI�͒��N�ł̐����Ƃ̔e���R���ɂ���Ɨ������Ă��܂����B
�@���̌�A�����͓����J��_�҂Ƃ��čs�����A�J��̏������i�߂���ƁA�V������ɑΐ����d�_���f������A�����̊Ԃőΐ����d�_�E�J��_���͂𑝂��A�J��_�҂̔w�����������ƂƂȂ����̂ł��B
�@���āA���̎����łɒ��N�̎�s����͕����ŁA�S�B���̂����_���R�͘a�������œP�ނ��Ă��܂����B�������啺�͂𑗂����ɓ����t�́A���炩�̐��ʂċǖʂ�ŊJ����K�v���������̂ł��B
�@�ɓ���6��13���̊t�c�ŁA�����������Ĕ_���R�̒����ɂ�����A�_���R������ɓ����������Ē��N�������v�ɂ����邱�Ƃ��A���ƌ�����悤��Ă��܂����B�t�c�͂���𗹏����悤�Ƃ��܂������A�J���]�ޗ����̔��Ō���ł��܂���ł����B
�@�����̊t�c��A�ɓ������P���� �������g�Ɖ�k���A�t�c�ɒ�Ă����ɓ��Ă����c���܂����B�����g�����{�R�̓P���������咣�����̂ŁA�ɓ��͑Ë����A���҂͓����I����ɓ��������R���P�� ���A���̌�Œ��N�������v�ɂ��ċ��c���邱�Ƃō��ӂ��܂����B���̈ɓ��E�����ӂ���������A�����J��͂Ȃ������̂ł��B
�@�Ƃ��낪6��13���ł̈ɓ��̒�ĂɁA6��15���̊t�c�ŗ�����
�E ���{�R��P�������Ȃ��Œ��N�̓������v�ɂ��Đ��Ƌ��c���s��
�E �����������v�ɕs���ӂ̏ꍇ�����{�P�Ƃœ������v��i�߂�
�Ƃ����ڂ̒lj��������܂����B����ɑ��āA���{�����ɓP���ɔ����鋭�͂ȁu�O�Ӂi�����̈ӌ��j�v�����݂��A���}�e�h�ɂ��ΊO���d�_�����܂�A9���̑��I����O�ɂ��Ĉɓ����t�͓P���ɓ��ݐ�Ȃ��Ȃ�A�ɓ��͂��̗����̒�Ă�����܂����B
�@6��16���A�����O���͟����g���ĂсA�t�c�Ō��肵�����j��`���܂����B����ɑ��āA21���A�����g��萴���̉��`�����܂����B
�E �����͂��łɕ��肵�Ă��苤�������̕K�v�Ȃ�
�E �������v�͒��N���{����s���ׂ����̂ł���A���{�͒��N����_���Ƃ��Ă���̂œ��ȂɊ֗^����͖̂������Ă���
�E ����������̓������݂̓P�����߂��V�Ï��ɏ]�����₩�ɓP�����ׂ��ł���
�Ƃ������̂ł����B
�@�����A�����̉������āA���{�Ɠ��������������t�c�́A�������c�c���i��A�������j�̔h�������߁A�����J��͕s���ł��邱�Ƃ��m�F���܂����B�����22���̌�O��c�ł́A���{�Ɠ������ɉ����A���M���R�p�L�����������`���Q�����āA�����̎咣�ɑS�ʑΌ�����ΐ��i��ꎟ������j�Ƒ�A�������̔h�����ŏI�I�Ɍ��肵�܂����B�����V�c�͐��{�̊J����j�ɉ��^�I�ł������A���t�E�������E���M�̈�v�����ӌ��̑O�ɁA�����̌�������F���܂����B
�@��A��������6��24���ɉF�i���o�����A29���Ɋ���x�O�̗��R�ɓ������������ɒ��Ԃ��܂����B
�@�A �p�I�̊���
�@6��30���A���V�A���~�n�C���E�q�g�����H�������g�́A���Ɠ��{�̓����P����v�����郍�V�A���{�̌����������𗤉��O���ɓn���܂����B�ɓ��Ɨ����O���͂�������ۂ��邱�Ƃ����߂܂����B�������A���ł�6��25���̃q�g�����H���g�Ƃ̉�k�ŁA�����O���͐����������Ȃ�������{����J�킷�邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ���������^���Ă���A���{������̋����ȑΐ��J��͍���ɂȂ��Ă��܂����B
�@����ɕ��s���āA�C�M���X���W�����E�E�H�[�h�n�E�X�E�L���o���[�O��������ɏ��o���A�j�R���X�E���f���b�N�E�I�R�i�[�������g����Đ��̈ӌ����m�F���������ŁA�����t�E�y�[�W�F�b�g�����㗝���g�ɑ��A���{���{�ɓ��������Œ��N�������v��i�߂�������m�F���A�������ɂ͗����R�̓����P�����K�v�ł��邱�Ƃ�`����悤�w�����܂����B
�@���{�ɂ̓��V�A�ƃC�M���X�̒�����ɋ��ۂ���͂͂Ȃ��A�ɓ��������O�����A�C�M���X�̒�������ꂴ����A�����ɑΐ��J����s�����Ƃ������{���̕��j�͍��܂��܂����B
�@�Ƃ��낪�A����7��9���ɁA���{�̓P���܂Ō��ɓ���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����\�z�O�ɋ��d�ȕԓ������������Y�������g�ɍ����܂����B10���ɂ́A������Y���I���g����A���V�A�̕��͊��͂Ȃ��Ƃ̏����A11���̊t�c�̓C�M���X�̒���������čs���Ă����ΐ����H����������āA�J�폀���̍ĊJ�����߂܂����B12���ɂ́A�C�M���X�̒�������ۂ������ɍ���N���鎖�Ԃ̐ӔC������Ƃ����������̑��t�����肵�܂��B
�@�B �����{�̎��_�ƊJ����_
 �@���{�̐ϋɓI�ȓ����ɑ��āA�Β��N���̐ӔC�҂ł��闛���͓͂��{�Ƃ̊J�����ɓ����Ă��܂����B�ނ͌R���g����i�߂����{�̓�����c�����āA���Ɠ��{�̌R���̎��Ԃ�m���Ă����̂ŁA�ɓ��������ē��{���������悤�Ƃ��Ă��܂����B
�@���{�̐ϋɓI�ȓ����ɑ��āA�Β��N���̐ӔC�҂ł��闛���͓͂��{�Ƃ̊J�����ɓ����Ă��܂����B�ނ͌R���g����i�߂����{�̓�����c�����āA���Ɠ��{�̌R���̎��Ԃ�m���Ă����̂ŁA�ɓ��������ē��{���������悤�Ƃ��Ă��܂����B�@����ŁA���_�̒��S�l�����������i���}�j�ƎႢ�c���⍲���鑤�߂������a�Ɨ������ł����B7��9���A�����ɖ��������摾�Y���g�ɑ��A�C�M���X�̒�������ۂ��鋭�d�ȕԓ���`���A���{�̊J��_���Ԃ点�܂����B
�@���̂��߁A�����͂͐������̔��Δh�ɋ�������A�ꋓ�ɑ�R�𑗂��ē��{�R�����|���悤�Ƃ��邵���Ȃ��Ȃ�A���Ǘ����͂́A7��19������R�� 2,300���̉��R�𑗂�o�����߂������A�ʂ� 6,000����֑���v��𗧂Ă܂����B
�@���{���͂��̑��������h���ɂ��āA���̑Γ��J��Ӑ}�����������̂ł���ƂƂ炦�A�J��ɓ��ݐ����ƂɂȂ����̂ł��B

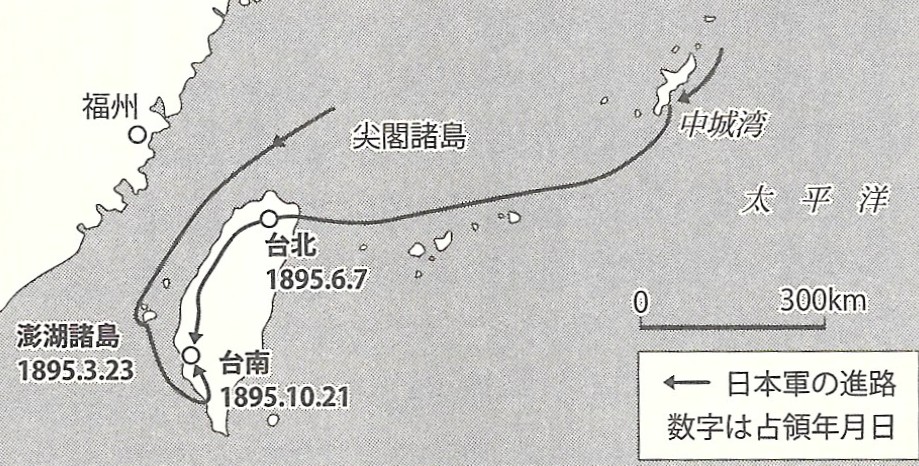
�����푈�iWikipedia�j
���֍u�a���Ƒ�p�i�U
�� �u�a���ƎO������
�@�@ ���֍u�a���
�@�����̍u�a�̖͍��́A�����ח��ォ��n�܂��Ă��܂����B�����C�ցi�Ŋցj�̓V�ÐŖ����O�X�^�t�E�f�g�����O�������{�Ɨ����̖͂����A1894�N11��26���ɐ_�˂ɓ������A���z�������Ɍ��m���ɖʉ�A�ɓ��ɉ���ė����͂̏��Ȃ�n�������|���q�ׂ܂����B���̂Ƃ��́A���{�̓f�g�����O�𐳎��ȍu�a�g�Ƃ͔F�߂������Ƃ��đΉ������A�ނ͗��̎莆���ɓ����ɗX�����ċA�����܂����B
�@���̌�A���{�Ɛ��ɒ��݂���č����g������ē����Ԃ̍u�a�����n�܂�A1895�N1��31���A�u�a�g�߂Ƃ�����������縗F�Q���L���ɗ��܂��B���̂Ƃ����S���ϔC��̌��͖��Ō��ɓ��邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�ɓ��Ɨ����O���͗��g�߂��L�͂Ō���������ƐM���Ă��������͂�S���g�߂Ƃ���u�a������]���Ă����̂ł��B
�@1894�N10��8��������{���{�͍u�a�������������͂��߁A�����͒��N�̓Ɨ��A�̓y�����A�������l���A�ʏ����̉�������q�Ƃ����Ă��쐬���ɓ��̗����Ă��܂��B���̌�A�č��̒��قɂ��L���u�a�k����O�ɂ��āA1895�N1����{�A�����͊t�c�ɍu�a�����������ē��ӂA�ɓ��ƂƂ��ɍL���Ɍ������A1��27���̑�{�c��O��c�ōu�a���Ă����肵�܂��B���R�͐�̂��������ɓ������̍L�͈͂Ȋ�����v�����A�C�R�͂܂���̂��Ă��Ȃ���p�������咣�������߁A�ɓ��Ɨ����́A���R�ƊC�R�̗v������ꂽ���Ă��쐬���āA�����u�a���߂����܂����B
�@�̓y�����ɉ����ču�a���������邩�A�̓y���������ۂ��đJ�s�����Ăł��Γ��푈���p�����ׂ����ŋc�_�͉��X�����A3��2���ɗ����͓͂��{�Ƃ̌��������t���āA�����ɂ������Ă͗̓y������ނȂ��Əq�ׂ܂����B���ꂪ�F�߂��A���͗̓y�����A�������x�����A���N�Ɨ����F�̎O�����ōu�a���ɗՂނ��ƂɂȂ����̂ł��B
�@3��20���̑����k�ŁA�����͍͂u�a��k�ɓ���O��Ƃ��ċx��������Ԃ��Ƃ��N���܂����B���{���́A21���̑���̉�k�ŋx��͌����������A�����u�a��W����Ƃ��ċx������ۂ��܂����B���́A24���̑�O���k�ŋx�����P�u�a���ɓ��邱�Ƃ�錾���A���{��������ɓ��ӂ��܂����B
�@����3��24���A��O���k���I����|�i�O��̐l�����ɂ����`�j�ɏ���ďh�ɂɋA��r���A�����͂����R�L���Y�Ɍ��e�ő_������A���ቺ�̖j�ɖ������܂����B�̑Γ��ᔻ��J�������V�c�͖��q�����������{�ƊO�Ȃ̐��ƍ����i���R�R�㑍�Ă�h�����Ď��Âɂ����点�A����4��10��������ɕ��A���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�����𗝗R�ɗ����A�����Č������f���邱�Ƃ����ꂽ���{�́A�����咣�����x�����F�߂���Ȃ��Ȃ����̂ł��B3��30���ɋx������A��p���O�Ώ������������ׂĂ̒n��Ő퓬���O�T�Ԃ̊����t���Œ�~����A�����Ԃ̌��͏I�����܂����B
|
�� ���֍u�a���̗v�_
�@�@ ���͒��N���Ɨ�����̍��ł��邱�Ƃ����F����B
�@�A ���{�ɑ��ėɓ������A��p�A�O�Ώ�������������B �@�B �R������Ƃ��Čɕ�����i���{�~��3��1100���~�j����{�Ɏx�����B �@�C ���Ɖ��B�e��������b�Ƃ��ē����ʏ��q�C���Ȃǂ�������A���{�ɑ��ĉ��ė��݂̒ʏ���̓�����^���A�V���ɍ��s�A�d�c�A�h�B�A�Y�B���J�s�E�J�`���A����ɊJ�s�J�`��ɂ�������{�l�̐����Ƃւ̏]����F�߂�B �@�D ��y��O�����ȓ��ɓ��{�R�͐�̒n���P�ނ��A���������ɏ��𗚍s���邱�Ƃ̒S�ۂƂ��ē��{�R���ЊC�q��ۏ��̂���B |
�@���̑��ɕʖ�ł͈ЊC�q�ۏ��̂ɂ��ċ�̓I�ɏ��������߁A�x����lj����ł͔�y��������5��8���܂��x����������邱�Ƃ��߂܂����B
�@�A �O������
 �@�����Ԃʼn��֍u�a��������ꂽ6�����4��23���[���A���V�A�E�h�C�c�E�t�����X�̎O�����̒������g���O���Ȃ��ѓ��O��������K�˂܂����B�ނ�͗ɓ������̓��{�ɂ��̗L�͖k���ɑ��鋺�ЂƂȂ�݂̂Ȃ炸�A���N�̓Ɨ���L�������ɂ��A�ɓ��̕��a�ɏ�V��^����Əq�ׂėɓ������̕����𔗂�܂����i�O�������j�B
�@�����Ԃʼn��֍u�a��������ꂽ6�����4��23���[���A���V�A�E�h�C�c�E�t�����X�̎O�����̒������g���O���Ȃ��ѓ��O��������K�˂܂����B�ނ�͗ɓ������̓��{�ɂ��̗L�͖k���ɑ��鋺�ЂƂȂ�݂̂Ȃ炸�A���N�̓Ɨ���L�������ɂ��A�ɓ��̕��a�ɏ�V��^����Əq�ׂėɓ������̕����𔗂�܂����i�O�������j�B�@�ɓ��n��ɗ��������C�M���X�E���V�A�����͓����Ԃ̊J�����̂��ߒ�������݁A�J�����C�M���X�ƃ��V�A�͋��͂��đ����̍u�a���߂����Ă��܂����B���֍u�a��c���n�܂�A����ʂ��ē��{�̍u�a���Ă�m��ƁA���V�A��4��8���A�ɗɓ�������������{�Ɋ������邱�Ƃ��Ă��܂����B�h�C�c���t�����X�͂���ɓ��ӂ��A�C�M���X�͓��{�Ƃ̑Η����D�܂��A�܂��u�a��̒ʏ��W�����̊g���m��A���ւ̎Q�������ۂ����̂ł��B���̂��߃��V�A���{�́A4��11���ɓ��ʉ�c���J���A�C�M���X�s�Q���̂��ƂőΓ������s�������c�_���܂����B
�@���̌��ʊ������肵�����߁A�����{��i11��8���ɓ������ҕt����ƕt���c�菑����������A���{�R���ɓ���������P�������j�ɂ͂���܂ŃC�M���X�̉�����x�����Ă������{�͈�]���ă��V�A�ւ̕s�M�����߂����ƂƂȂ��Ă����܂����B
�� ��p�̍R�������ƒ��N�̋`������
�@ ��p�̍R������
 �@�O�����̌��ʗɓ������𐴂Ɋҕt�����̂ŁA���֍u�a���Ŋl�������̓y�͑�p���O�Ώ��������ƂȂ�܂����B���{���{�͌R�ߕ������R���I�叫���p���ɔC���A�߉q�t�c�i�t�c���k����{�\�v�e�������j�ƂƂ��ɑ�p�Ɍ������V�̓y��ڎ�����悤�����܂����B
�@�O�����̌��ʗɓ������𐴂Ɋҕt�����̂ŁA���֍u�a���Ŋl�������̓y�͑�p���O�Ώ��������ƂȂ�܂����B���{���{�͌R�ߕ������R���I�叫���p���ɔC���A�߉q�t�c�i�t�c���k����{�\�v�e�������j�ƂƂ��ɑ�p�Ɍ������V�̓y��ڎ�����悤�����܂����B�@��p�ł́A���{�̗̓y�ƂȂ�̂����ۂ���緈��b��n���L�͎҂���p�ȏ����i�Ȃ̒����j���i���ɓƗ��𔗂�A�������������5��25����p���卑�����ɏA�C���܂����B�����Ɂu�Պ��v�i���}�j�������Ƃ����A�W�A�ŏ��̋��a�����a�����A�t�����X���͂��߂Ƃ��鏔�O���ɉ����Ə��F�����߂�ƂƂ��ɁA���{�ւ̕��͒�R�����݂��̂ł��B
�@�����̈����n���ψ����o�F�����R�́A6��2���A����̉��l�ۑD��ő�p����葱�����s���܂����B�߉q�t�c��5��29���A��̓�������㗤���J�n���A��Ƒ�k���r�I�ȒP�ɐ�̂��A��k���̈ȑO�ɓ��i���͑嗤�ɓ��S���܂����B������6��17���ɑ�k�ő�p���{�̎n�������s���܂����B
�@�������߉q���������R���`�E�R�̏P�����A��p�암�ɏ㗤���đ����̂���\��ł������A����ύX���đ�k���ӂ̎������m��������A��i��}�邱�ƂɂȂ�܂����B
�@���{�R�̐N�U�ɑ��đ�p���͌�������R���܂������A10��19���A���{�R�S�R�����U���Ɉڂ���p���卑�͖ŖS���܂����B���������R����11��18���A��{�c�ɑ��āu����S���S������ɋA���v�ƕ��i��p����錾�j�����̂ł��B�������A���{�R����̂��Ă����̂͑�p�̐����ɉ߂����A��p��[�̍P�t�ȓ�ƁA��p�����A��p���Z������炷�R�x�n�т͖���̂ł��������߁A����Ȍ����p�̐퓬�͒����������ƂɂȂ�܂����B
�A ���N���{�E�Q�����i���������j�Ƌ`������
�@�O������A���N�ł͓��{�̓���������{�ɋ��͂��ĊJ�������i�߂���O�W���t�ɔ����鐨�͂̓��V�A�ւ̐ڋ߂�}��A�����̍��@���{�܂�����ɓ������܂����B
�@���̊ԁA5��21��������O�W���t�����O�W�Ɩp�j�F�̑Η��ŕ������A5��31�����p��z���t���������A�p�j�F�������������ĉ��v��i�߂܂����B�������A�p�j�F���{�܈ÎE�v����^���7��6���ɓ��{�֍ēx�S�������̂ł��B���̌��ʁA���O�W���t���������A8��24���A��O�����O�W���t���������܂����B
�@����A���{���{�ł͍u�a���̔�����A1895�N6��4���Ɋt�c�Łu�V�Ίؕ��j�v���������A�O������̏�f���āA�u�����̑Ίؕ��j�͐���ׂ������i��j�ߒ��N�����Ď��������ނ���j�������v���ƁA���Ȃ킿�����푈���̂悤�ȘI���ȓ��������s�\�ƂȂ������Ƃ��m�F���A���}�Ȓ��N���S���E�d�M�̗����Ɛ���������߂܂����B
�@��オ���N�𗣂ꂽ��T�Ԍ��10��8�������A�{�܂̎E�Q��������������̂ł��B���N�̓d�M������{���Ŋm�ۂ����������ƍl������{�c�́A���̈ӎv����̒��S�ɂ�������㑀�Z�i�Q�d��������{�c��⋑��āj�̈ӎv�������A�O�Y���g�͐��ƘA������茋�����Ċ������ƁA������ɓ��Ɨ����O�����ٔF�������A���R�̈ꕔ��C�R�̒��Z�A����ɖ��Ԃ́u�s�m�v�����Č��s�����̂ł��B
�@�O�Y���g�������\�ꓙ���L�������S�ƂȂ��āA���V�A�ƌ����{�ܔr�����v�����A���N���{�ږ�����{���V���𒆐S�ɁA�̎��و��Ɨ̎��x�@���A�F�{�����}���Ŋ������В������B�����Ȃǂ̓��{�l�Q�l�A���钓���̌��������ꔪ����i�O�����j�����s�ɂ�����܂����B
�@�O�Y���g���{�E�Q���A��@�N�̎w���̉��ɋN�����ꂽ���N���{���̌��͓����ɂƂ��Ȃ��N�[�f�^�̂悤�Ɍ��������悤�Ƃ��܂������A���{���ł͎��q������ �̃_�C��V�A�l���z�ƃT�o�e�B���ɖڌ�����āA���̂悤�Ȋ�݂͎��s���܂����B�܂��A�{�����̏ڍׂƓ��{���{�̐^�����B�����Ƃ���s�����ȑΉ��́A�� �����N��K�₵�Ă����w�j���[���[�N�E�w�����h�x���̑啨�L���W�����E�A���o�[�g�E�R�b�J�����̋L���ɂ���Đ��E�ɓ`�����A�������ᔻ����܂��B
�@���{���{�͊W�҂����҂��A�O�Y���g�ȉ�49���̖��Ԑl�͍L���n���ٔ����̗\�R�ɁA�R�l8���͑�t�c�R�@��c�ɕt����܂������A1896�N1���A�R�@��c�͌R�l8�l�S�����Ƃ��A�n�ق̗\�R�͎O�Y��̎����֗^��F�߂����̂́A�E�Q���̏��s���̂��ߏ؋��s�\���Ƃ��đS����Ƒi���܂����B�܂��A���N�ł��{�E�Q�����̌�Ő���������l�����O�W���t�̉��ōٔ����s���A��������O�������Y���ꖋ�������}���܂����B

���N���E�Q�Ɠ��{�l �N���d�g��ŁA�N�����s�����̂��@�@�����q ��
�@�{���́A����܂Łu�{�܂̎ʐ^�v�Ƃ��đ����̖{�Ɍf�ڂ���Ă����P���̎ʐ^�̍l����n�܂�܂��i���́j�B�T���́A�č���C�^���A�A�t�����X�ŏo�ł��� �����Ђ�G���ɂ܂ŋy�сA���̍ŏ��̌f�ڎ��͓����푈���ɔ��s���ꂽ���{�̎ʐ^���ł��邱�Ƃ��˂��Ƃ߂��A�B�e���ꂽ�����͉��܂ł͂Ȃ��A�{��̏��� �ł���ƒf�肳���̂ł��B
�@����͈��ł����A�{������ʂ��Ă���͓̂O�ꂵ�����؎�`�ł��B�\�E���̌��g�قƓ����̊O���Ȃ��{�c�Ƃ̊ԂŌ��킳�ꂽ�d�M�L�^�̂ق��A���{�Ɗ؍��Ŕ��s����Ă���L�^��W�҂̉�z�^�ȂǁA�L�͈͂ɂ킽��j������g���邱�Ƃɂ��A�����̑S�e��������������܂�
�@���҂́A�߉^�̉��܂����܂ꂽ1851�N���炿�傤��100�N���1951�N�ɓ��{�Ő������ݓ��̏��������҂ł��B
�@����܂ŁA���R�����̒��N���g�E�O�Y��O����d�҂Ƃ�������I�Ȏ����ƌ����Ă������̎������A���͓��{���{�ƌR���ɂ������ɏ������ꂽ�d���������� �����Ƃ��������{���́A���ؗ����̗��j�����ɑ傫�Ȉ�𓊂���ƂƂ��ɁA���̎������ߑ���{�ƒ��N�E�؍��Ƃ̊W���l�����Ō��������Ƃ̏o���Ȃ��d �厖���Ƃ��Ĉʒu�Â��Ȃ������Ƃ����܂��B
|
�� ���q�i�L���E�����W���@Kim Moonja�j �@1951�N�A���Ɍ��ɐ��܂��B70�N�A���{���k�썂���w�Z���B79�N�A�ޗǏ��q��w���w���C�m�ے��I���B79�N4������86�N3���܂œ���w���w������B98�N4�����猻�݂Ɏ���܂ŁA����w�����⍲���B �@�_�����u�p�]���̎��w�����n���V�̐���𒆐S�Ɂv�i�w���N�j������_���W�x17���A1980�N3���j�u��������ȋ����x�ɂ��Ą��������@�𒆐S�Ɂv �i�w�����N��x24���A�ޗǏ��q��w���w���A1981�N3���j�u�O�E��^���Ƌ���A�����Ɨ����菑�����𒆐S�Ɂv�i�w�J�y�j���x29���A�ޗǏ��q��w�j�w ��A1984�N3���j |
�@���{����h�����ꂽ�����g���A���C���̎�s�ʼn��܂����R�ƎE�Q����Ƃ��������ׂ��s�ׂɂ��āA���{���{�͗��狭������A���N�ł́A���ꂪ�E�Q���ꂽ���������ݏ������Ƃ������O�W���t�ւ̕s�M�Ɠ{�肪���܂�܂����B
�@1895�N12��30���A���O�W���t���f��������t���܂����A�`���I��w�҂����́A�f���߂͕��ꂩ����g�̔����������A���N�`���̗��ʑ����Đ�����͕킷��`�i���{�j�ɂȂ炤���̂��Ɣ�����܂����B�ނ�͉��E�Q�ƒf���ߔ��z�ɕ���A�����Ɣ��J���h���X���[�K���Ƃ��āA�e�n�ōR���`�������ɗ����オ�����̂ł��B
�@���N���{���`�������ւ̑Ή��ɖZ�E����Ă���ԂɁA��l�����O�W���t�Ŕr������Ă����哴�h�����͐W�E�����p�炪�N�[�f�^���N�����A1896�N2��11���A�ނ�̓��V�A���g�E�F�[�x���ƒ�g���A���V�A�����Ɍ쑗���ꂽ���������V�A���g�قɈڂ��A�p��z����ǂƂ���V���t���������܂����i�I�ٔd�J�j�B
�@�e���I�ȊJ���h�͈�|����A���{�̉e���͈͂�C�ɒቺ���A���V�A�̒��ڂ̉���������A�����푈�̐푈�ړI�ł������������v�Ƃ��̔w��œ��{���i�߂Ă���������̕ی썑���͍ŏI�I�ɍ��������̂ł��B
| �� �@ | ���g�b�v�� | ���p�������� �� |